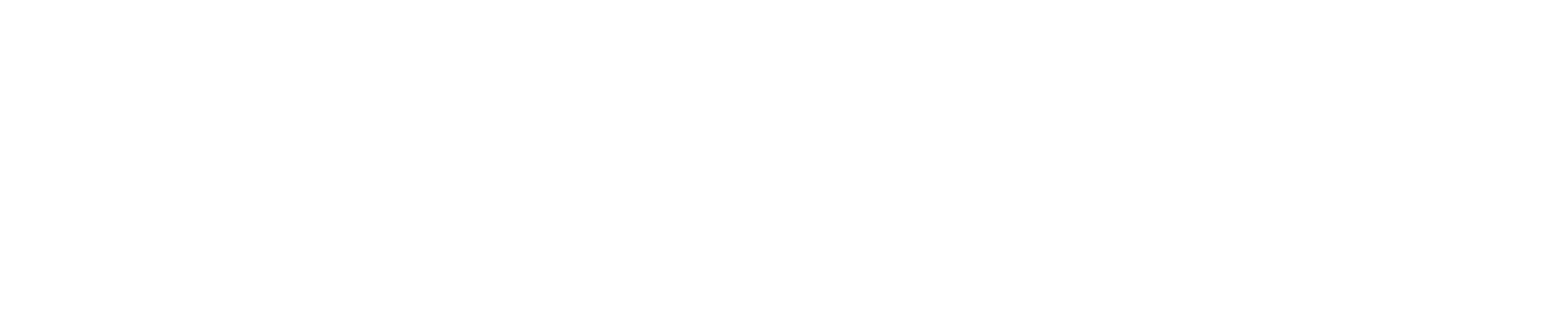|
|
|
年末年始の相撲部屋は慌ただしい。一般家庭と同様に大掃除を行い、恩人知人へ出す年賀状の枚数もハンパじゃない。部屋や一門によっては餅つきをやったり、稽古場にしめ縄や御幣を飾ったり、元旦から初詣出や挨拶回りに出かけ、あるいは挨拶回りにやってきた人々を迎え、チャンコも普段とは趣向を変えた「おせち料理」系のものを作る。そんなこんなで親方も力士も、おかみさんも、部屋のありとあらゆる人間が忙殺される。 だからといって稽古を休むわけにもいかない。初場所の初日に調子のピークを持っていこうと思ったら、暮れの最終週から「松の内」にかけて、いちばん体をいじめておく必要がある。力士たちは元旦こそ稽古を免除されるが、2日の朝ともなれば普段通り稽古をしている。稽古をしなくていい元旦でさえ、稽古場でシコやテッポウに汗を流す若い衆もいる。今年の初場所初日は1月8日だったから、元旦の1週間後が初日。のんびり正月気分に浸った力士など誰もいないことだろう。 |
 |
|
1年に6場所、奇数月のたびに本場所が行われる。本場所のない偶数月は地方巡業がある。たった1つ、この2月を除いては。 2月は、まるまる一と月を部屋で過ごせる。そういう意味では、力士が最もリラックスできる月だ。住み慣れた部屋で過ごしながら、稽古に専念して英気を養うことができる。稽古が終わった後は趣味に没頭したり、飲み食いに出かけたり。パチンコ屋や競馬場でチョンマゲ姿の大男をよく見かけるのも2月だ。だから角界では昔から「本当の正月は初場所が終わってから」と言われている。 故障箇所を治したり、古傷を癒したりできるのも、この時期しかない。現在のように「公傷」制度が撤廃されてからは、力士はケガを押して土俵に上がり続けることを余儀なくされている。まるっきり歩けないとか立てないという重症でない限り、全休して大きく番付を下げるよりは、ダメモトで出場して一つでも星を稼いでおいたほうがいい。そんな力士たちがいっせいに病院やリハビリ施設に出かけるのも2月特有の現象だろう。 ケガがしにくくなる方法が2つある。1つは相撲を取らないこと。これは現役力士にとっては引退もしくは廃業を意味するから問題外。もう1つは、体を鍛え、充分に調整すること。骨や腱を「筋肉」というヨロイで固め、その上から「脂肪」というクッションで覆ってしまえば、自ずとケガはしにくくなる。そのためにはよく稽古し、よく食べ、よく休むこと。けっきょく2月は人一倍稽古に励むべき月でもあった。 (2005/02/01) |
| バックナンバー 次のエッセイを読む |